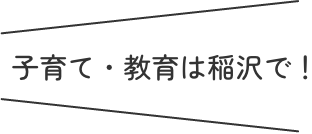障害福祉サービス
- [更新日:]
- ID:1500
福祉サービスの種類
障害のある方への福祉サービスは、個々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村において、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施される「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を利用する場合には「介護給付」、訓練等の支援を利用する場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用できる対象者や、必要な手続きが異なります。詳しくは問い合わせてください。
また、「地域生活支援事業」については、次のページに掲載しています。
障害福祉サービスの種類
介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
ヘルパーの派遣により、自宅で入浴、排泄、食事の介護等を行います。 - 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時の移動の補助などを総合的に行います。 - 同行援護
視覚障害者で移動に著しい困難がある人に、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供します。 - 行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 - 療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 - 生活介護
常に介護を必要とする人に、日中の間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 - 短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、施設において、宿泊を伴う短期間の入浴、排泄、食事の介護等を行います。 - 重度障害者等包括支援
常に介護が必要な人の中でも、介護の必要性が非常に高い人に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行います。 - 施設入所支援
施設に入所する人に対し、夜間や休日の入浴、排泄、食事の介護等日常生活の支援を行います。
訓練等給付
- 就労定着支援
就労移行支援等を利用して一般企業等に新たに雇用された人の生活面の課題に対応し、就労の継続を図るために関係機関との連絡調整等、必要な支援を行います。 - 自立生活援助
居宅における自立した生活を送るために、定期的な訪問等により相談に応じたり、関係機関との連絡調整をするなど、必要な援助を行います。 - 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 就労継続支援(A型=雇用型・B型=非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
相談支援給付
- 計画相談支援・障害児相談支援
障害のある人の自立した生活を支え、障害のある人の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス利用計画・障害児支援利用計画を作成するサービスです。 - 地域移行支援
障害者支援施設等に入所している障害のある人または精神科病院に入院している精神障害のある人が、地域で生活するための住居の確保やその他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等に応じます。 - 地域定着支援
施設や病院から退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行した方などに対し、常時(夜間も含む)の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等の相談に応じます。
障害児通所支援
- 児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 - 医療型児童発達支援
児童発達支援および治療を行います。 - 居宅訪問型児童発達支援
障害児通所支援を利用するために外出が著しく困難な障害児に対して、居宅を訪問して発達の支援を行います。 - 放課後等デイサービス
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 - 保育所等訪問支援
障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
利用者負担額
原則、利用したサービスに要した費用の1割に相当する額となります。ただし、世帯の所得に応じて「負担上限月額」が決められており、1か月に利用したサービスの量にかかわらず、「負担上限月額」以上の負担は生じません。
また、入所施設における食費や光熱水費などの実費や、通所サービス等における食費などは自己負担となりますが、低所得のかたに配慮したさまざまな軽減措置があります。詳しくは問い合わせてください。
| 区分 | 世帯の範囲 |
|---|---|
| 18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障害者本人と配偶者 |
| 障害児(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
| 区分 | 世帯の所得などの状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護(または中国残留邦人等支援法による支援給付)受給世帯 | 0円 |
| 低所得1 | サービスを利用する本人の年収が80万9千円以下の市民税非課税世帯 | 0円 |
| 低所得2 | 低所得1に該当する方以外市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市民税所得割額が16万円未満(18歳未満は28万円)の市民税課税世帯 ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く。 | 9,300円 (18歳未満は4,600円) |
| 一般2 | その他の市民税課税世帯 | 37,200円 |
まずは、ご相談を!
サービス利用を希望するかたは、市役所福祉課・支所または相談支援事業所にご相談ください。
| 事業所名 | 電話 | ファクス |
|---|---|---|
| 障がい者サポートセンターいーな※ | 0587-23-2162 | 0587-33-4666 |
| 障がい者サポートセンターまつのき※ | 0587-96-7755 | 0587-96-7711 |
| 障がい者サポートセンターこうのみや※ | 0587-22-7110 | 0587-22-6110 |
| サポートセンターひまわり(18歳未満)※ | 0587-22-5807 | 0587-22-5808 |
| 障害者相談事業所いぼりの里 | 0587-35-2000 | 0587-35-2300 |
※「医療的ケア児等コーディネーター」がいます。
医療的ケア児等コーディネーターとは、医療的ケアを受けながら生活しているかたのさまざまな相談をお受けし、必要なサービスを総合的に調整する役割を担っています。