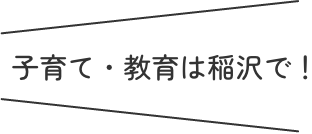よくある質問
自主防災訓練がマンネリ化しています
- [更新日:2020年7月13日]
回答
自主防災訓練で、消火器、AEDや三角巾の使用方法を習得するのも効果的ですが、たまには、違った視点から防災訓練を見直してみるのもよいかも知れません。
1.防災マップづくり
地域の人たちがより安全に避難場所まで逃げるには、どの道を通ればよいでしょうか。
地域の危険箇所のほか、いざというとき避難できそうな空地、街頭消火器など役に立ちそうな物がまちには眠っているかもしれません。
自分たちのまちをよく知る上で防災マップづくりは有効です。
狭い道路、その道路に面するブロック塀、看板、道路に面する大きなガラス、自動販売機など危険箇所が非常に多いことがわかります。
自分たちに必要なマップの内容にしていくためには、定期的な見直しも必要です。
2.避難所体験
体育館に一泊し、実際の避難所で起こりそうな問題とその解決を擬似体験します。
そこで、避難所生活で起こりそうな問題を準備し、発表された問題に対してどんな解決策がありうるかアイデアを出し合い、みんなでどの案が良いかを話し合いましょう。
また、宿泊を強いる必要はないので、子供たちだけではなく、広く地域の老若男女に来てもらいましょう。
わずかな時間でも、災害時に本当に必要なものは何か、近所付き合いが大切であることなどに気付くことができます。
3.災害時避難行動要支援者の把握
高齢の方や障害のある方など(災害時避難行動要支援者)は、災害時に避難所まで簡単には避難できません。
そこで、被災直後の安否確認を含め、避難支援の方法を平常時から決めておきましょう。
そのためには、地域に関わる人たちみんなのチームワークが大切です。地域をよく知る人、福祉の仕事をしている人など、さまざまな人の協力を求め、要支援者が話しやすい環境をつくり、要支援者一人ひとりにつながるパイプを増やすことを心がけましょう。
机上で作成したプランなどが現実に有効であるか確かめるために、実際に訓練をしてみるのも良いです。
お問い合わせ
稲沢市役所 建設部 防災安全課 災害対策グループ(防災安全課)
住所: 愛知県稲沢市稲府町1番地
電話: 0587-32-1275
ファクス: 0587-32-1158
電話番号のかけ間違いにご注意ください!