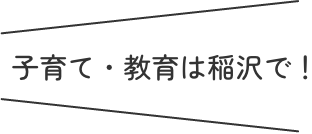よくある質問
自主防災活動って何をすれば良いのですか
- [更新日:2019年1月30日]
回答
「共助(自主防災活動)」と言うと、多くの方が災害発生直後の活動を思い浮かべるのではないでしょうか?
災害発生直後の自主的な活動が大いに役立っていることは、先の災害で証明されています。
しかしながら、日頃から準備をしていなくては、自主防災組織があったとしても災害時には機能しません。
自主防災活動は、災害時の活動と平常時の活動の両方が重要となります。
平常時の自主防災活動には大きく分けて次の2つのことがあります。
1.自助力強化の啓発
災害時に、「生き残る、怪我をしない、自力で対処できる」ようにするためには、日頃から個人や世帯単位での災害への備えが必要となります。
こうした自助力を強化するために、自主防災組織には以下のような地域住民一人ひとりの防災意識を向上させる活動が求められます。
- 各家庭での非常食等の準備(最低7日分の水や食料の備蓄など)促進
- 家具の転倒防止器具・住宅用火災警報器などの設置促進
- 各家庭での家族間の安否確認方法の確立促進 など
2.共助力の強化
1995年(平成7年)の阪神淡路大震災において、災害発生直後は市役所をはじめとする防災関係機関の支援(公助)には限界があることが明らかになりました。
このような状況においては
普段から顔を合わせている地域住民が互いに協力し合いながら災害に対応しなければなりません。
しかし、日頃近所付き合いのない人が、災害発生直後に地域住民と急に親しくなることは難しいものです。
地域に積極的に関わっていこうとすることは自助になりますが、日頃から地域住民が連帯し、協力し合える風土を作っていくことも必要になります。
自主防災組織には、日頃から地域住民が互いに顔見知りとなり、協力し合える風土を作り出すため、以下のような活動が求められます。
- 各種イベントの開催
- 地域住民同士が相互に顔見知りになる機会を提供することが重要であり、必ずしも防災訓練を行うことに限りません
- あいさつ運動などの実施
- 防災意識(災害時には住民間の支え合いが重要でること)の啓発活動の実施
- まずは、班・ブロック単位で、日頃から互いに協力し合える風土を作ることから始めると良いでしょう。
- 災害発生時の役割分担の明確化
災害時に「誰が何をするのか」、「誰が誰をサポートするのか」など、役割を明確にすることが大切です。
全ての住民が「地域全体のためにやるべきことがある」という意識を持つことが重要です。
普段の活動例
- 防災に対する心構えの啓発
(研修会への参加など) - 災害発生の未然防止のための地域活動
(地域の巡回など) - 災害発生に備えて地域を知るための活動
(避難場所等の把握など) - 災害発生時の活動を習得するための活動
(消火、避難訓練など) - 災害発生時の活動に備えるための活動
(機材や備蓄品の管理など)
※稲沢市では、自主防災組織を対象に防災倉庫内に備蓄する資機材の購入補助制度がございますので、ご活用ください。
災害時の活動例
- 情報収集伝達活動
(救援情報の伝達など) - 初期消火活動
(消火器による消火活動など) - 避難誘導活動
(安否確認や介護が必要な人への援助など) - 救出救護活動
(負傷者の救護など) - 給食給水活動
(救援物資の避難所への運搬・分配など)
お問い合わせ
稲沢市役所 建設部 防災安全課 災害対策グループ(防災安全課)
住所: 愛知県稲沢市稲府町1番地
電話: 0587-32-1275
ファクス: 0587-32-1158
電話番号のかけ間違いにご注意ください!