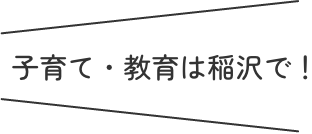市長コラム(令和7年度)
- [更新日:]
- ID:4728
令和8年2月

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」が好調だそうです。物語の進行が早く、織田信長の若い頃は描かれず、勝幡城が出てこないのは少し残念ですが、この地方が舞台になるのはうれしいものです。
私は稲沢市六角堂で生まれ育ちました。秀吉の妻・寧々の養父、浅野長勝の邸宅跡は六角堂長光寺のすぐ南にあり、子どもの頃の遊び場の一帯なので思い入れも深いものがあります。六角堂は清洲城下から近く、信長家臣の屋敷があったとしても不思議ではありません。
長光寺には他にも信長ゆかりの伝説や物があります。「臥松水(がしょうすい)」は信長愛飲の水の井戸と言われています。彼は好んでこの水を茶の湯に用い、遠く岐阜城までも運ばせたと父から聞いています。今は涸れて水が出ないのは悔しく思います。いつかはこの水を使って「信長茶会」のようなものを長光寺でやってみたいと考えています。
重要文化財六角堂の参拝口の上に掛かる県指定文化財「鰐口」は埴原加賀守常安の寄進と伝わるもので、加賀守は長光寺辺りで寝泊まりしていたところ信長に召し抱えられたとも言われています。長光寺にお参りに行かれた時はぜひ頭上を見上げてください。
長光寺は江戸時代の美濃路沿線にあり、近くには「清洲代官所」へ渡る「役所橋」があったり、四ツ家追分にあった道標も門前にあります。この道標の文字は尾張藩右筆の「丹羽盤桓子」の筆によるものと伝わっています。
子どもの頃多くあった格子の家は少なくなりましたが、街道の趣きを楽しんでいただけます。
ぜひ戦国時代や江戸時代に思いを馳せ、長光寺や六角堂周辺を歩いてみてください。きっとタイムスリップすることができますよ。
令和8年1月
市民の皆さんにおかれましては輝かしい令和8年の新年をお迎えのことお喜び申し上げます。
昨年は物価高騰など暮らしにくさを感じられることも多かったかと思われますが、然るべく早い時期に政府から示された「物価高騰対策重点支援地方交付金」を活用した支援をお届けします。
また、憲政史上初めての女性首相である高市内閣の発足により、支持率も上がりさまざまな面で注目されています。
一方で、災害が多い年でもありました。年末には北海道三陸沿岸で地震が発生し、青森県八戸市などで大きな被害が出て、後発地震注意情報が発令されるなど、今後に不安を残す原因となりました。
さて、今年はどんな年になるでしょうか。スポーツの分野では、3月に大谷翔平選手も参加を表明した野球のWBC(ワールドベースボールクラシック)が開催され、サムライジャパンが連覇を目指します。9月に愛知名古屋では第20回アジア競技大会、引き続き10月には第5回アジアパラ競技大会が開催され、本市の豊田合成記念体育館(エントリオ)がハンドボールの会場となりますので、市民皆さんの応援よろしくお願いします。
本市もたくさんの課題を抱えています。徐々にではありますが、人口が減少しています。昭和40年代50年代に構築した公共施設やインフラが老朽化し、更新の時期を迎えていますが財政にその余裕がありません。人口や経済が右肩上がりだった時代の考えは通用しない時期を迎えています。ですから余計に事務の効率化やデジタル化をスピード感を持って進めなければなりません。
市民病院の経営悪化も財政を苦しめる大きな課題の一つです。昨年末以来、国に対する要望を、自治体病院を持つ首長として多くの市とともにしてきました。一定の成果は出てきていますが、本年の診療報酬の改定がどうなるか注視しなければなりません。
農業や農地の課題も浮き彫りになってきています。担い手の高齢化や不足により遊休農地化が進んで環境が悪化しています。また、農業関係団体の役員のなり手不足が深刻です。この問題にも手をつけなければなりません。
市長になって10年目を迎えました。責任の重大さは自覚しています。これまでの経験を活かし皆さまの意見をよく聞き、決断と実行をしてまいります。ご支援よろしくお願いします。
令和7年12月
年の瀬です。日経トレンディ2025年のヒット商品ベスト30で、1位が大阪関西万博withミャクミャクでしたが、2位に映画「国宝」が入りました。観客動員数は1000万人を超えたそうで、実は私もその一人です。本物の歌舞伎にまで消費が及んだと言われています。
先日、NHK Eテレ「古典芸能への招待」で「仮名手本忠臣蔵」七段目、十一段目を観ました。これも「国宝」関連消費の一つかもしれません。
12月と言えば忠臣蔵。
まず「仮名手本忠臣蔵」の仮名手本の意味からお話しします。江戸時代、習字の手本として「いろは歌」が使われました。「いろは」は「ん」を入れると48文字ですが、もともと47文字のもので、討ち入りした浪士の数と同じ四十七あるため仮名手本とつけられました。では「忠臣蔵」とは何か、「蔵いっぱいの忠臣」とも「大石内蔵助にかけた」とも言われます。
史実としての「赤穂事件」と、歌舞伎や人形浄瑠璃の「仮名手本忠臣蔵」は大きく異なりますが、江戸城松の廊下で勅使饗応役浅野内匠頭が、高家筆頭吉良上野介に刀を抜いて切り付け傷を負わせたもので、将軍徳川綱吉は即日、内匠頭に切腹を申しつけ、播州浅野家はお家断絶、大石内蔵助以下御家人は路頭に迷うことになります。しかし、内蔵助以下47人は艱難辛苦を乗り越え翌元禄15年12月14日(旧暦)、上野介邸に討ち入り、見事に本懐を遂げるという物語です。この事件は当時の江戸っ子に大変な反響を呼び、翌元禄16年にはすでに題材として歌舞伎にかかったようです。
しかしながら、これ以降赤穂事件のように実際にあった事件を直接題材とする歌舞伎などが大量出現したので、幕府はこのような出し物を禁じました。
竹本義太夫による人形浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵」が世に出たのが寛延元年(1748年)。登場人物の名前も変え、時代背景も太平記の時代に変え、巧みに幕府の法度を乗り越え、民衆の拍手喝采を浴びました。歌舞伎もほぼ同時期に「仮名手本忠臣蔵」として定着します。討ち入りは西暦に直すと1703年なので、45年後に今私たちの目に触れる形になったようです。
以後歌舞伎や芝居の業界では、昔から客の入りが悪くなったら「忠臣蔵」を上演したと言われます。
言われなき屈辱に耐えに耐えて、忠義を果たす内蔵助と四十七士、それを取り巻く人間模様が、歌舞伎界の大看板になったという「忠臣の手本」、年末恒例のお話でした。
令和7年11月
11月22日にそぶえイチョウ黄葉まつりが始まります。毎年20万人以上の観光客が、稲沢市祖父江地区を訪れる本市にとっても一大イベントです。
どうして大勢のお客様が祖父江を訪れるのでしょうか。黄金色に染まるイチョウの黄葉がフォトジェニックだからなのでしょうか。大粒でもちもちする「藤九郎」を始めとするぎんなんが、手軽で安価に手に入るからでしょうか。もちろんそのどちらも叶うからなのだと思われます。
名鉄尾西線の赤い電車が黄色いイチョウの間を縫って走る姿もテレビ等でよく取材され、写真や絵画コンクールなどでも取り上げられる題材です。若い女性が立派なカメラを持って写真を撮るところを見ると、この景色も豊田市の「香嵐渓」と並んで、県内の秋の行楽地として選ばれているのだと思います。
一方、ぎんなんの生産量も全国一と言われ、関東方面の居酒屋などでも「祖父江ぎんなん」としてお馴染みとなっています。JA愛知西の「ぎんなんブランド部会」会員の皆さんが塩水選別などで、ブランドとしての質を落とさぬようさまざまな努力を惜しまず生産してみえることに敬意を表したいと思います。
令和3年にオープンした「祖父江ぎんなんパーク」がまつりの会場となります。名鉄尾西線、山崎駅の目の前ですので、ぜひ電車でお越しください。お待ちしています。
「歯をもつてぎんなん割るや日本の夜」加藤楸邨
令和7年10月
10月、読書の秋です。
子どものころ身体が弱かった私は、本を読むこと、絵を描くことなどの室内遊びが自然と多くなる日々を過ごしていました。幼少時は絵本を読むこと、小学生になると当時急速に発行部数を増やしてきた週刊少年漫画雑誌「週刊少年マガジン、サンデー、キング」をむさぼるように読んでいました。「マガジン」は調べると昭和34年3月創刊、「サンデー」も同年創刊、「キング」は昭和38年7月創刊で、叔母に付いていった名古屋で創刊号を買った記憶があります。「マガジン」には野球漫画「黒い秘密兵器」、戦争漫画「紫電改のタカ」があり、その後「巨人の星」で漫画の虜になってしまいました。「サンデー」では「伊賀の影丸」、「サブマリン707」などが大好きでした。後発の「キング」では「0戦はやと」などを読んでいたと思います。私より後の世代の方たちは「週刊少年ジャンプ」や「週刊少年チャンピオン」の影響を受けた人が多いと思いますが、「ジャンプ」は昭和43年7月、「チャンピオン」は隔週刊で昭和44年7月に創刊されており、私がすでに週刊漫画の世界から去った後の出来事でした。その後の私は、小学校高学年で「怪盗ルパン」の世界にはまり、中学生以降の松本清張好きにつながっていきます。一方で、小学校6年生の時だったと思いますが、宮崎康平さんの「まぼろしの邪馬台国」という本に出会い、古代史に対する興味を急速に深めていきました。以後も、少年漫画や、友達の影響で見始めたプロレス、野球などのスポーツ関係や、政治、哲学、思想の面で惹かれていった三島由紀夫、小林秀雄などの書物を精力的に読んでいきました。沢木耕太郎や村上春樹に対しても、60歳手前で急速に目が悪くなる前は良い読者でした。
何よりも私は書店という空間が大好きです。図書館より圧倒的に書店が好きなのです。人類が考え構想し、あるいは夢想したものが形になった本、書籍というものがうずたかく積まれ、並んで売られている書店。これらは今、かつてない危機を迎えています。平成26年度には約1万5千店あった書店が、令和6年度には約1万店に減少しており、この10年間で約3割の店が閉じられたことになります。全国の市町村の約3割は書店が1店舗も存在しない「書店空白地域」となっているそうです。本市においても個人経営の書店の閉店、スーパーやショッピングモール内の書店の撤退、規模の縮小が相次いでいます。若者の活字離れ、本をインターネット通販で買う人が圧倒的に多いことがその要因だとは理解できますが、寂しい限りです。
私たちにあの新刊書の香りを嗅がせてくれる至福の場所を提供する経営者は現れないでしょうか。あるいは、公が手を差し伸べる時が来ているのでしょうか。
令和7年9月
9月になりました。サンマのおいしい季節です。私は一番好きな魚はと聞かれると、「サンマ」と答えるようにしています。子供のころ七輪で焼いたサンマが大好きでした。長じてからも丸ごと焼いたサンマのはらわたの苦さや、身と掛けられた塩が絶妙のバランスを醸し出すあの独特の味は、私にとって魚の王様にふさわしいものです。
「目黒のサンマ」という落語があります。大正時代くらいに成立した落語のようですが、ある日お殿様が急に馬に乗り遠出をいたします。目黒辺りで休憩をするのですが、何も食べず屋敷を出てきたことからお腹が空きます。そこへ何かを焼いているようなおいしそうな香りがただよってきます。お殿様があの良いにおいのするものを食したいと言うものですから、家来たちは農家の軒下で焼いているサンマを手に入れ主人に食べさせます。すると、脂の乗ったサンマのおいしいこと、お殿様は家来に「サンマは庶民の食べる下魚だから屋敷に帰ってもだれにも言わないように」と口止めされても、その味は忘れられません。別の日、親戚筋から招待され「何か食べたいものはあるか」と問われた時、思わず「サンマを食したい」と口走ってしまいます。驚いた先方は急遽魚河岸へ馬を走らせサンマを調達し、蒸して脂を抜き、毛抜きで小骨まで抜いて椀物にしてお出ししたのですが、以前食べたサンマの味にはほど遠く「このサンマは、どこで仕入れたのか」と尋ねられる、「日本橋の魚河岸でございます」との返答に、お殿様「それはいかん、サンマは目黒に限る」という落ちとなります。これもサンマがイワシなどとともに庶民の食べ物であるところのいわゆる下魚とされていたところからくる話でありまして、昨今の漁獲量の大幅減少(2014年以前の年間20万~30万トンと比べると、2022年には1.7万トン、少し回復した昨年2024年でも3.9万トン)による高値、2022年には1尾350円から400円の高値で店頭に並んだそうです。もはや大衆魚ではなく、高級魚に近いものになってきています。不漁の原因も海面水温の上昇による漁獲域の変化が大きいといわれており、ここにも地球温暖化の影響が表れてきているのかと愕然とします。
さて、サンマとカタカナで表記してきましたが漢字では「秋刀魚」と書きます。秋の時期に出回り、青く切れ味鋭い刀のような形をした魚ということから大正時代、佐藤春夫の詩「秋刀魚の歌」がきっかけとなってこの漢字表記が広まったようです。そんなに古い話ではないのですね。いずれにしても、安価で大量にサンマを食べることができる時代がもう一度やってくるといいですね。
令和7年8月
7月17日、ギリシャ共和国オリンピア市から、アリスティディス・パナギオトプロス市長ら中学生を含む全11名の訪問団が来日され、翌18日には、市役所を公式に訪問されました。中学生のホームステイ事業は、平成30年以来7年ぶりのことでした。
ホームステイの最終日21日に行われた同事業の報告会では、オリンピアの子ども達や、受け入れ側の市内のご家庭の生の声を聞くことができて、短期間でこれほど仲良くなれるものかと強く感じ、不覚にも涙がこぼれました。7年前もそうでしたが、私にとっても感慨ひとしおでした。
ギリシャ共和国オリンピアの人々と接していると、さまざまな思いに駆られます。勤勉で時間を守ろうとする我々日本人に対し、時間にルーズ(2度のオリンピック聖火採火式においてもいやというほど経験していますが)、しかし、明るく前向き、楽天的でその時その時を精一杯楽しもうとするその精神。その姿を目の当たりにすると、逆に私たちの日々の暮らしや、働き方は本当にこれでいいのかと考えさせられます。アリス市長は「半年間市長職を入れ替わってみませんか?」と冗談のように発言されました。ひとつ喫煙、飲酒の習慣をとってもそうですけれど、日本人が戦後の長い期間の成果として勝ち取ってきたと思っている生活習慣に対してでさえ、価値観は一つでないのだと気づかされます。
さて、今年度後半のNHK朝の連続テレビ小説{ばけばけ}は、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の妻・セツを主人公としたもの(ドラマはもちろんフィクションです)だそうです。ハーンはギリシャ共和国レフカダ島の出身であり、島根県松江市で日本の昔話や怪談に興味を持ち、濃密な執筆生活を送り、東京都新宿区で没せられました。そのような事情から、きっとギリシャに対する国民の関心も高まることでしょう。
そして再来年には、本市とオリンピア市が姉妹都市提携をして40周年を迎えます。ちょうどロスアンゼルスオリンピックの開催年にもあたりますので、両都市間で民間レベルでの交流も含め盛り上げていこうと、市長同士は同意しています。
国と国、都市と都市の関係は一朝一夕に成るものではありません。両市の先人のご尽力と努力に敬意を表し、未来志向でさらなる友好関係の強化を図っていきたいと考えています。
令和7年7月
今年は盛夏の訪れが早そうです。
真夏の食べ物というと、私にはのど越しがよい「そうめん」と「ひやむぎ」が思い起こされます。
子どものころは、ひやむぎしか食べなかったような記憶ですが、高校に入学し地理歴史研究部に入ってから、古代史の研究のため奈良によく行くようになり、三輪そうめんのおいしさを知りました。冷たく冷やしたそうめんがつるつるとのどを通っていくあの感覚は、暑い夏には格別です。
そうめんには日本三大産地があるようです。播州そうめん(兵庫県)、三輪そうめん(奈良県)、小豆島そうめん(香川県)です。私は最初に言った経緯から、三輪そうめんに一番親しみがあります。古代史のメッカでもあります山の辺の道、三輪大社の付近で夏に食べるそうめんは、汗も引き、一服の涼ともいえるものです。
皆さんは「そうめん」と「ひやむぎ」の違いはどこか知っていますか。その違いは太さにあるようです。JAS 規格に定められていて「そうめん」は直径1.3mm未満の麵を言います。一方「ひやむぎ」は直径1.3mm以上1.7mm未満の麺を言うそうです。ただ、手づくり(手延べ麺)の場合、直径1.7mm未満の麵は「そうめん」、「ひやむぎ」とどちらを名乗っても問題ないそうです。
製法上の違いでは、小麦粉を塩水でこねて生地を作り、油を塗りながら手を使って細く伸ばす麺が「そうめん」、平らな板と麺棒を使って生地を薄く伸ばし、刃物で細く切る麺が「ひやむぎ」とか「うどん」となるそうです。
歴史的に言うと、古いのは「そうめん」のようで、奈良時代に中国から伝わり、そのもとは「索餅(さくべい)」と呼ばれる菓子だったようです。
「ひやむぎ」の起源は室町時代にさかのぼり、麦粉だけをこねて「索餅」のように細く切った麺「切麦」が生まれて、それを冷やして食べる「ひやむぎ」が生まれたとのことです。
7月7日は、全国乾麺協同組合連合会が定めた「七夕・そうめんの日」です。七夕にそうめんを食す習慣を持つ地域もあるようです。中国の言い伝えでは、7月7日に亡くなった帝の子どもの霊が疫病を流行らせたため、好物であった「索餅」をお供えしたところ疫病が治まったことから、それ以降七夕の日に無病息災を祈念して「そうめん」を食べる風習ができたようです。
いずれにしても、さっぱりした「そうめん」、「ひやむぎ」を食べて暑い夏を乗り切りたいものです。
令和7年6月
6月、梅雨の季節です。この時期毎年日本のどこかで洪水被害が起きていることに心を痛めています。
以前にも一度このコラムで書いた藤沢周平の「蝉しぐれ」の中には、主人公の父が大雨の時、あらかじめ切ると決めてあった河川の堤防を農地の少ない場所で切り、城下を守り農地の被害も最小限にとどめたという描写があります。このような手法は現代ではもう使われませんが、かつては水防の常とう手段だったようです。実際江戸時代、木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)において堤防の高さには差があり、木曽川左岸の堤防が最も高かったようです。その差は三尺(約1メートル)あり、御三家である尾張徳川家を水害から守るものであったといわれています。そのため美濃(現在の岐阜県)側では、輪中堤(集落や田畑を洪水から守るため地域全体を取り囲むように築かれた堤防)が発達しました。
また同じような話としてこの地方には「小田井人足(おたいにんそく)」という言葉があります。庄内川が増水して危険になると尾張藩は、名古屋城下を守るため右岸に住む小田井村(現在の名古屋市西区小田井)の人々に堤を切ることを命じました。人々は堤を切ることによって田畑に被害が及ぶのは自分たちだと、働いているふりはしましたが、わざと時間をかけ水が引くのを待っていたそうです。そのようなことからこの地方では働かない「なまかわ(怠け者)」な人足を「小田井人足」と呼ぶようになったという、地元の人にとっては不名誉な話です。
そのような過去から最近では「流域治水」という考え方が主流となってきました。
国土交通省は、地球温暖化など気候変動による災害の頻発化・激甚化を踏まえ、堤防の整備、ダムの建設・再生などの対策を一層加速するとともに、集水域(雨水が河川に流入する地域)から氾濫域(河川等の氾濫により浸水が想定される地域)にわたる流域にかかわるあらゆる関係者が協働して水害対策を行う考え方に大きく舵を切ってきました。これを流域治水と言っています。
どこかにあらかじめ被害を受けるところを作っておくのではなく、関係者が協働して被害の軽減を図る、新しい時代の水害対策は時代に合わせ大きく変化しているのです。
令和7年5月
風薫る5月です。皆さん5月病などにかからず、さわやかに活動したいですね。
今月は4月12日に山形県天童市にて開催されました「織田信長サミット」について書きたいと思います。
まず「織田信長サミット」とは何かですが、信長ゆかりの自治体の関係者が一堂に会し、歴史と文化土台に魅力あるまちづくりを共に考え、交流を深めていくことを目的としたもので、信長生誕の地を観光の目玉にと考えている本市にとっては初めての参加となりました。参加自治体は山形県天童市(今年の開催地で織田宗家が治めた織田藩最後の地)、群馬県甘楽町(かんらまち、信長二男信雄を初代藩主として8代152年にわたって織田家が統治した小幡藩の所在地)、静岡県富士宮市(本能寺の変で発見されなかった信長の首を持ってきてつくったといわれる西山本門寺に信長公首塚がある)、名古屋市(勝幡城で生まれた信長が移り住んだ那古野城の所在地)、愛知県清須市(那古野城から移り住み尾張の中心として発展した)、豊明市(上洛を目指した今川義元を破った桶狭間の合戦が行われた場所)、小牧市(信長が初めて自ら築城し城下町まで整備したといわれる小牧山城がある)、岐阜市(天下統一をめざし稲葉山の頂に岐阜城を築き賓客をもてなした、楽市楽座もここから始まったといわれる)、福井県越前町(信長をはじめとする織田一族の発祥の地とされる、劔神社が氏神)、滋賀県近江八幡市(本能寺の変によって失われたが、信長が人生最後に築城した豪華絢爛な安土城があった場所)、信長生誕の城勝幡城のある本市も含めて11の市町で構成されています。
織田信長は天文3年(1534年)に稲沢市と愛西市の境にある勝幡城で生まれたことが今や学会でも定説となっています。また来年のNHK大河ドラマは信長に仕え、その後天下統一を果たした豊臣秀吉とその弟秀長を主人公とした「豊臣兄弟」と決まっており、この尾張地方が前半の主な舞台となることが予想されます。信長公生誕の城「勝幡城」にも脚光が当たり、本市にも歴史好きな方々がたくさん訪れてくれないかと期待しています。
そして、あと9年後の2034年は、信長生誕500年の記念の年となります。この年を何とか盛り上げることができないか、作戦を練っているところです。
歴史好きな人にもいろいろな時代の愛好家がお見えですが、戦国時代は武将やそれを取り巻く女性たちにも夢やロマン、悲劇もあり、特にファン層が厚いといわれます。「織田信長サミット」に参加したことをきっかけに、本市の夢も広がっていくといいですね。
令和7年4月
4月1日、令和7年度が始まりました。
新しい年度、公務員にとっては今年2度目の正月が来たようなものです。
市民のことをまず第一に考える公務員として、我々稲沢市役所職員は今年度も全力で職務に専念いたします。
さて、ビッグプロジェクトの話題を2つ。
一つは新濃尾大橋の完成です。長きにわたり仮称新濃尾大橋と言ってきましたが、この度仮称が取れ正式名称が新濃尾大橋と決定いたしました。この橋を含む現道は県道羽島稲沢線で、橋はなくとも西中野渡船によって交流が続いていましたが、今回の架橋整備によって一宮市、稲沢市と岐阜県羽島市を結ぶ太いパイプが出来上がることになります。そして慢性的に渋滞していた濃尾大橋の混雑解消が図られ、ヒトモノの行き来が活発に遅滞なく行われようになることに大きな期待が寄せられます。5月24日に予定されている開通式が待ち望まれるところです。
そしてもう一つのビッグプロジェクトは一宮西港道路です。一宮西港道路は名神高速道路一宮 JCT から東海北陸自動車道を南進する形で伊勢湾岸道路に接続する高速道路で、この3月に国土交通省社会資本整備審議会 道路分科会 中部地方小委員会において3つあったルート帯案が、中央ルートに決定いたしました。
この案は総工費1兆2500億円から1兆5000億円が見込まれるとともに、集落・市街地を極力回避し人口集中地区の通過面積は最も少ないものとなっています。日本最大の海抜0メートル以下地帯面積を誇る西尾張地域の住民にとって災害時の避難路、救援物資の輸送、あるいは一時避難場所としても活用が可能かと期待を寄せるところでもあります。
一方で産業力強化の点でも大いに貢献します。東海北陸自動車道一宮 JCT から名古屋港(鍋田交差点)の所要時間が現状65分かかっていたものが約17分に短縮され、交通の速達性、定時性が格段に向上します。また、物流交通と生活交通の分離が図られ、一般道の渋滞解消や交通事故の減少が見込まれます。
本市にとっては市を縦断する初めての自動車専用道路の建設であり、その与える影響や効果については計り知れないところではありますが、期待が圧倒的に大きいことは事実です。完成まであと何年かかるか予想できませんが、私たちの心を揺さぶるビッグプロジェクトであることは間違いありません。