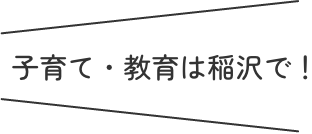市長コラム(令和6年度)
- [更新日:]
- ID:3868
令和7年3月

「世の中に たえて桜のなかりせば 春の心は のどけからまし」(在原業平)
桜がいつ咲き始めるのか、いつ満開になるのか、いつ散るのか、桜の花は古来から人の心を悩ませたものだということが、この句からも分かります。
実際、昨年の「平和さくらまつり」は、1月からの暖冬傾向を受けた私の助言が災いして、3月30日に開催したところ、3月に入ってから寒さが続いたことにより、30日にはほとんど開花が見られず、当初の予定通り4月6日開催のほうがよかったという結果に終わりました。私も心のどかな春の日を送ることができませんでした。
その原因は、「休眠打破」が想像以上に鈍かったからだとみられています。1月2月の極端な温暖化傾向の中、2月中旬からは休眠状態から成長の段階に入ると思われていましたが、実際はそうではなかったようです。
それでは「休眠打破」とはいったいどんなシステム(構造)なのでしょうか。桜の花芽は開花前年の夏にはできていて、それが秋から冬にかけて成長しないように休眠状態に入って年を越します。厳寒の時期、低温刺激を受け休眠から目覚めるのです。このことを「休眠打破」と言います。そして蕾が膨らみ開花に至るわけですが、東京の場合400°Cの法則と呼ばれるものがあるようです。2月1日を起算日として毎日の平均気温を足していき、400°Cを超えると開花し始めるという法則です。この計算方式で3日以上ズレないともいわれています。もう一つ600°Cの法則と呼ばれるものもあります。起算日は同じなのですが、毎日の最高気温を足していき、600°Cを超えると開花するものです。
いずれにしても桜の開花時期は、多くの人の頭を悩ませるものですが、私が注目したいのは「休眠打破」の方です。人の一生にも「休眠打破」は必要なのではないかと思います。すべての人が等しく持っている花芽が、真冬の厳しい寒さを耐えて目覚め、美しい花を咲かせるのです。大切なのは「休眠打破」のきっかけです。毎年の開花時期がなかなか予想できないように、一人一人の人生において花が咲く時期はさまざまですが、そのきっかけは必ず真冬の寒さを経験しないと訪れないことを肝に銘じて、職員の皆さんには年度末の忙しい職務に励んでいただきたいと思います。また能力があるのに仕事上の花が咲かないとお思いの皆さんへの言葉といたします。
令和7年2月
2月といえば、天下の奇祭「国府宮はだか祭」ですが、今回は少し違った話をしたいと思います。
私たちの小学生のころ(昭和30年代後半から40年代前半)稲沢市の自慢といえば、日本三大操車場の一つである稲沢操車場があることと教えられました。ちなみにあと二か所は神奈川県の新鶴見、大阪府の吹田です。
先日(1月16日)JR 貨物稲沢駅開業100周年の記念式典が、井之口側の貨物線路と旅客線路の間の会場で開催されました。100周年の記念のロゴマークを付けた DF200 形式の「Ai-Me」(機関車ボディに愛知県と三重県の風景をラッピングしてある)と、EF64 形式の貨物車の出発式も同時に行われました。稲沢操車場は大正14年(1925年)1月16日に名古屋駅から移転、開業して満100年が経過したまさにその日に式典は行われたわけです。
調べますと、操車場(ヤード)の区分は、平面ヤード、ハンプ(坂阜)ヤード、重力ヤードと大きく分けて3つになるようです。そのうち稲沢操車場はハンプヤード方式であるといわれ、人工の丘(ハンプ)から坂道を貨車を転がり落とし、仕分け線まで送るもので、規模は大きくなるけれども、仕分け効率は最も高いものだといわれます。
第二次世界大戦中は、戦時物資の輸送などで貨物輸送量は増加しましたが、米国による空襲の標的となり、終戦の直前8月2日と14日に爆撃を受け、2日には職員、動員学生3名が負傷し、その機能が1日弱にわたって麻痺し、14日には1名が死亡、3名が負傷したという悲しい記録も残っています。
戦後の経済成長による貨物輸送需要の拡大で、稲沢操車場には蒸気機関区というものがあり、そこには 2つの転車台と2つの扇機関庫が備えられていました。転車台とは、蒸気機関車や片運転台形機関車を少ないスペースで進行方向に向ける設備で、扇型の機関庫と相まって輸送量の増大を支えたものと思われます。
しかし、昭和58年に、集結輸送方式から拠点間直行輸送方式への拡充が発表され、昭和61年には稲沢操車場は廃止されました。翌年には国鉄民営化により客貨分離が行われ、規模が縮小されたことは、時代の流れとは言え、線路わきに育った私にとっては寂しいことでした。
時代は今、鉄道貨物輸送に有利な状況になってきています。カーボンニュートラルの実現が追い風になっているからです。トラックによる陸上輸送も変わっていくのでしょうが、電気機関車や電気式ディーゼル機関による輸送が今後も50年、100年と続くことを願ってやみません。
令和7年1月
令和7年の初春を寿ぎ、謹んで市民の皆さんのお幸せをお喜び申し上げます。
お正月ですからビシッとした話をしたいと思い、我々公務員やサラリーマンのかつての必需品、ネクタイについて話します。“かつての”と書いたのは、愛知県の職員さんが11月になってもネクタイをしていないので調べたところ、10月1日付け人事局長からの通知で「職員の軽装勤務の通年化について」というものが発出されており、男性については年間を通してノーネクタイでもよいことを知ったからです。
「初日の出 見えず ネクタイ緩めけり」
「事務始め 雇員 ネクタイを新にせり」
などの句があって、昔は初日の出を拝むときもネクタイを締めて、仕事始めの日にはネクタイを新品にしてというような人が多かったのではないかと思います。
私もネクタイをすることによって気持ちがビシッとする一人です。特に年が改まって「仕事始め式」にその年初めて出勤する時は、どのスーツでどのネクタイをしていこうかと考えてしまいます。首元が締まることによって身も心も引き締まるような気がするからです。
最近は特に若手IT企業経営者などTシャツ、ジャケット、カジュアルパンツにスニーカーといったスタイルが多いように感じます。仕立てのいいスーツにYシャツ、レジメンタルネクタイに革靴は時代遅れのような気がしてなりません。スティーブ・ジョブズさん、堀江貴文さんなどが、私にそのような印象を与えているのかもしれませんが、IT産業に従事している人たちにとってはむしろ働きやすい服装こそが、あるいは新しい発想がわきやすい服装こそがすべてであって、余分なことに神経を使いたくないのでしょう。
ジョン万次郎が初めてネクタイを日本に持ち込んだ人だそうで、琉球に上陸したのが1851年です。その後薩摩藩、長崎奉行所などで長い尋問を受けたようですが、その所持品目録に「襟飾3個」とあり、これが「ネクタイ3本」を意味していたというのが通説となっています。明治維新を迎え服装も洋装になり、さまざまなネクタイが登場しましたが、現在のようなネクタイが主流になったのは「昭和」の時代になってからのようです。
昭和の時代に生まれ、平成、令和と生きてきた私たちにとっては、ネクタイが公人のしるしであるような気がします。高齢者のたわごとと思っていただいて結構ですが、仕事始めぐらいはネクタイをビシッと締めて臨みたいと思います。
令和6年12月
1年が過ぎるのも早いもので、12月師走を迎えました。
11月17日に行われました稲沢市長選挙におきまして、市民の皆さんのご支援とご理解をいただき、3度目の当選を果たすことができました。責任の重大さに身の引き締まる思いです。次の4年間も全力で市民が安心して暮らしていける市政運営をして行く覚悟です。
人間が古くなってきましたので、昔のことがよく思い出されるのですが、昭和30年代40年代はまだ、庶民の人情が残っていたと思います。インターネットでのお買い物なんてないですから、買い物は対面でした。同じ町内にあった八百屋さんや、かしわ(鶏肉)屋さんに母が書いてくれた紙を持ってお使いに行くのですが、どのお店の人も顔見知りですので、幼い私でも買い物は簡単にできました。小さい商いをしてみえるお店が多かったですが、そこには社会の構造を垣間見る体験がありました。
スマートフォンからほとんどすべての買い物や手続きができる社会が到来することは歓迎すべきことなのでしょうが、人と人のふれあいのない商売は味気なく思いますし、市役所の職員が温もりのない会話しかできなかったなら、来庁された市民の方々からは、苦情が寄せられることでしょう。
Z世代という言葉があります。生まれた時からインターネットに親しみ、物心ついた時からスマートフォンがある1990年から2010年までぐらいに生まれた人たちのことを言います。情報を得る手段が私たちのように、新聞やテレビではなく、インターネットやYouTubeなどのSNSからだということが一番大きな特徴です。つまり、人と相対で接すことが少なくても情報が得られ、生活を営んでいくことができるのです。
今後はこの世代が社会の主導的役割を担って行きます。世の中変わるでしょう。 しかし、不易と流行という言葉があるように、人間は人間として変わってはならないこともあります。信頼であったり、共感であったり、思いやりです。 年の瀬、不易なものもあることを信じて歳を越したいと思います。
令和6年11月
先月10月20日に「ブラアイチ in 稲沢 2024」を、愛知県と本市主催で開催いたしました。
国府宮参道の中高記念館を出発点に、尾張の国国衙跡の碑、美濃路稲葉宿本陣ひろば、三宅川の河道を広げるため行っている権現橋の架け替え工事、三宅川の堤防敷を歩いてもらったり、国府宮の第一鳥居から三菱エレベーター試験棟のソラエを眺めてもらい出発地へ戻るというものでしたが、幸い天気にも恵まれ多くの愛好家に参加いただき、歩いてもらいました。お題は「天下の奇祭国府宮はだか祭のルーツは 奈良時代にあり」でした。
このお題には我が市を流れる三宅川が大きく関わっています。現在の三宅川は稲沢市の市街地北端に端を発していますが、私が古三宅川と呼ぶもの(歴史的には二之枝川と言うそうです)その上流を流れており、稲沢の歴史的な遺跡に大きく関係しています。市内の古老から三宅川は、国府宮の太鼓橋に端を発していると聞いたことがありますが、まさに古三宅川はここを通っています。古代から国衙関連施設はこの川流から少し離れた微高地に位置しており、江戸時代に開通した美濃路はこれらの河川が作り出す自然堤防を縫って走っています。本陣跡ひろばの東側道路を北へ眺めてみますと、その高低差がよく分かっていただけます。
これらの旧河川敷地が住宅開発されたところは、どこも排水が悪く浸水の危険度が高いと言わなければなりません。そこで本市ではこれまでさまざまな対策を進めてきました。三宅川本川の河道改修、井堀橋や正楽橋などの架け替えによる河道確保、稲沢公園バラ園横の雨水貯留管理設などです。西町の区画整理区域内でも遊水池の整備、権現橋の架け替えなどです。南大通り線の大和橋の架け替えが済み、そこまでの河川改修が国や県の力で完成すれば、古代からの懸案が解決するのも遠くない将来なのではないでしょうか。
「水を治める者は国を治める」古代中国春秋時代斉国の宰相管仲の言葉です。水害や干ばつによる被害は経済発展と社会秩序の安定にとって重大な影響を及ぼすことは今も昔も変わりありません。
現在の私は中小河川の一つも十分には出来ていませんが、今後も努力を続けてまいります。
令和6年10月
縄文と弥生と聞いて何を感じますか。
私たち昭和30年代から40年代にかけて義務教育を受けたものは、縄文時代と弥生時代はともに土器の名称が由来の呼称で、縄文時代は基本的に狩猟・採取生活を送っており、弥生時代は米の栽培が始まったことによって大規模な灌漑事業などが必要となり、貧富の差が生まれ後の時代の大君のさきがけとなった時代であると習いました。
そのように教えられた私は、現在でも主食である米を作り始めた弥生人が、現在の日本人の先祖だったと勝手に思い、あの独特の意匠を持つ縄文土器は日本人の美的意識からは離れたところにあるものだと感じていました。
しかし最近、縄文土器や土偶の豊饒な表現力に大いなる魅力を感じています。
大阪万博の太陽の塔の製作や「芸術は爆発だ」の発言でおなじみの岡本太郎氏は、縄文土器の芸術性を高く評価していたそうです。きっかけは昭和26年の上野の国立博物館での縄文土器との出会いにあったようです。「驚いた。こんな日本があったのか。いやこれこそが日本なんだ。身体中の血が熱くわきたち、燃えあがる」と語りました。私とは比べ物にならないくらいの、高い感性を持った芸術家ならではの出会いと発見だと思います。
私は平成30年に東京国立博物館で開催された特別展「縄文-1万年の美の鼓動」を観に行きました。青森県の三内丸山遺跡(これまでの縄文観を覆すような遺物の出土があった)からの出土物、木製編籠(縄文ポシェットと呼ばれる)はもちろん、国宝に指定されている土器、土偶などが多数展示されていて壮観でした。縄文土器はその名のようにまだ柔らかい土器製作の途中の土に縄目を押し付け独特の文様を作り出していることが共通の特徴です。しかし、各地から出土した土器はそれぞれ独特の情念や地域性に裏打ちされたかのような意匠が施されており、観れば観るほど、古代人の想像力の豊かさと表現力に感心するばかりでした。
つい最近、NHKBS「フロンティア 日本人とは何者なのか?」を観ました。後で知りましたが昨年12月に放送したものの再放送だったのですが、人骨をDNAゲノム解析をすると、現代日本人は東アジアの人々のグループと異なり、むしろ古代縄文人のDNAに近いことが分かったそうです。日本人が独特のDNAゲノムを持つのは縄文人の遺伝子を受け継いだからなのでないかという大胆な仮説が示されました。
私の直接の祖先は弥生人でなく、縄文人だったのかもしれないと、自分の顔を見てまじまじと思ったところです。
令和6年9月
先月8日に日向灘でマグニチュード7を超える地震が発生し、政府は南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)を発令しました。この地方においては何事もなく1週間が過ぎ、15日午後5時には本市においても第二非常配備を解き、通常の警戒態勢に戻りました。昨今の気象も災害も激甚化、頻発化しており一刻たりとも警戒を怠ることが出来なくなってきています。
9月は、災害とは切っても切り離すことが出来ない月です。その中でも忘れてはならないのは、65年前、昭和34年9月26日に襲来した伊勢湾台風です。当時私は4歳でしたので、おぼろげな記憶しかありませんが、この地方を襲い、台風史上最大の被害を記録し、災害対策基本法の制定に繋がったこの台風について書きたいと思います。
昭和34年(1959年)9月26日は、おり悪くも本市制施行後最初の稲沢市議会議員選挙の投票日でした。市史によると台風15号(伊勢湾台風)の強烈さもその進路が、この地方にとって最悪であることも昼過ぎにはすでに予測されていたようで、午後6時頃、潮岬付近に上陸したときの中心気圧は929.5mb であり、愛知県西部では午後9時から10時ごろに最も風が強くなりました。風雨と倒木(美濃路の松並木もこの時に多くが倒れた)のため、各投票所からの投票箱の輸送が遅れ、ろうそくの光を頼りに開票事務が開始されたのが、午後8時15分だったと言います。ようやく開票が終了しそうになった頃、ますます強くなる風は、10分間平均風速 37m/秒、瞬間最大風速50m/秒に達したそうです。市の全職員は、非常体制につき、夜を徹して救助対策の手配に忙殺されたと言い伝えられています。
同年9月29日現在の記録が残っていますが、稲沢市における被災者数3,407人、死者6人、重傷者13人、軽傷者24人、住居全壊157戸、半壊450戸、床下浸水81戸、非住家の被害1302戸、冠水した田959ha、同畑15ha、橋梁流失3か所だったそうです。記録に残る市災害史上最大であったことは間違いありません。
私たちはもう一度、この台風をしっかりと記憶しておられる方が多いうちに、記録にとどめる活動をしなければならないのかもしれません。巨大地震は完全に予知することは不可能ですが、台風の進路については、当時より格段に予想精度は向上しています。市民の皆さん、避難や家の周りの片づけなど、日のある明るいうちにできることをしてください。そして、これは地震被害にも言えることですが、日頃の備蓄、緊急持ち出し品の確認整備など、災害への備えはくれぐれもお忘れなく。
令和6年8月
「暑いですね」が合言葉のようになっている今日この頃です。酷暑が続いています。国連のグテーレス事務総長は昨年の7月27日に「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来したのです。呼吸ができないほどの空気。耐え難い高温。化石燃料から得る利益と気候変動に対する不作為のレベルを受け入れることは、到底できません。指導者たちは先導しなければなりません。もはや躊躇は要りません。言い訳も不要です。誰かが先に動くのを待つのは、もうやめましょう。そんな時間は、もうありません。」と語りました。この数年特に昨年の7月は暑かったのです。今年はどうでしょうか、昨年以上に暑いような気がします。皆さん、熱中症には十分お気をつけください。
本市も令和3年9月2日に「ゼロカーボンシティ宣言」を行い、2050年カーボンニュートラルを目指して着実に取り組みを進めています。
8月11日には二十四節気の立秋、暦の上で秋の始まりを迎え、22日には処暑、厳しい暑さの峠を越えたころとなります。もちろん暦の上のことで昨今の異常気象では、第二第三の峠がその後に待っているかもしれませんが、秋が一歩ずつ近づいてきます。
国民の休日である山の日も11日ですが、日曜日にあたりますので翌12日が振替休日となります。13日から旧盆、15日には精霊流しを行う方も多いのでしょう。先祖を思い出し供養する時期なのでしょう。
6日は広島、9日は長崎の原爆慰霊の日、15日は終戦記念日と先の大戦の記憶を呼び覚まし、平和の尊さを改めて考える時期でもあります。30日には稲沢市戦没者追悼式が行われます。戦後79年、戦争を経験した人の数も減り、戦争の思い出や悲惨さを語る人もめっきり少なくなってしまいました。記憶を呼び覚ましと書きましたが、本や映画あるいはテレビ番組等からの情報に想像力を加えて、戦争は起こしてはならないとの固い決意をこの時期に多くの人に持ってもらいたいと思います。
9月1日には、稲沢市総合防災訓練を平和中学校で開催します。1月1日に起きた能登半島地震の教訓を現実に取り込むためにも、各種団体の協力を得て、さまざまな事態を想定した大掛かりな訓練をいたしますので是非ご参加ください。
沸騰するような気温の日が続く8月となるでしょうが、市民の皆さんにはご自愛いただきますようお願い申し上げます。
令和6年7月
猫の額ほどの面積ですが、家庭菜園をしています。今の時期、夏野菜の収穫が朝のほっとするひと時です。若い時は野菜作りを自分がするなんて思ってもみなかったですが、父が亡くなってから同じ程度の面積を耕しています。
おいしいものを作って食べることが好きです。最近では年齢のせいでしょうか、子供のころに食べていたものが無性に懐かしく思い出されます。あまり好きでなかった十六ささげ(我が家ではささげといっていた)を今育てています。花が咲きそこからささげが伸びてきます。見ていてなかなか面白いものです。
先日、愛知西農協の「地産地消まつり」農産物品評会表彰式に出席しました。稲沢市長賞は平和町の生産者による「白ダツ」に贈られました。若い方はダツ自体もご存じないかもしれませんが、里芋などの茎の部分(ズイキともいう)のことです。「白ダツ」はその部分に紙などを巻いて、日光が当たらなくして白く育てたものです。私が子どもの頃よく食べた「赤ダツ」と違って、色白で上品、京都あたりの高級料亭で消費されるものだと聞いています。昔私が食べていた「赤ダツ」は里芋の茎の部分で、処理をして乾燥させると長期間保存が可能なので、食糧事情がよくない頃は重宝されたものです。おふくろはよくイカと一緒に煮ていました。しかし、もう何年も食べていません。「赤ダツ」自体も見かけた記憶がありません。一方「白ダツ」は平和町の特産と聞いてはいましたが、この職に就くまでは実際にどう作られているかは知りませんでした。今ではその地域を車で走っていると生産現場に出くわします。この間白ダツを自分で調理しましたが、アクを取る、酢を入れてゆでる、氷水で締めるなど手間のかかる工程を経てようやく口に入るようになります。時間に追われる現代人には馴染まない食材なのかもしれませんが、手間をかけた分、とても美味しくいただきました。
6月16日放送のNHK「ヒューマンエイジ 人間の時代 第3集・食の欲望 80億人の未来は」は非常に示唆的でした。私もおいしいものを作って食べることが好きだと書きましたが、金に糸目をつけず辺鄙な田舎にまで美食を追い求めるフーディーと呼ばれる人たちがいる一方、世界の大半の人たちが数種類の穀物由来の加工食品でその胃袋を満たしている。穀物由来の食品によって世界80億人のおなかを満たすことは地球環境に大きな負荷をかけ、私たち自らの健康をも害することに陥っていると、専門家は警鐘を鳴らしているとこの番組は教えてくれました。もう一度自分の体を形作っている「食」についてよく考えてみようと思います。
令和6年6月
6月1日(土)から、第33回稲沢あじさいまつりが、大塚性海寺歴史公園で始まります。多くの方々にご来場いただき、色とりどりのあじさいに、ひと時心を休めてもらうことができれば幸いです。
6月の花といえばあじさいですが、松尾芭蕉の句に「紫陽花や帷子時(かたびらどき)の薄浅黄(うすあさぎ)」があります。帷子とは、夏に着る薄手の衣のことです。浴衣(浴衣)という言葉の語源は昔、ふろに入るときに着用した「湯帷子(ゆかたびら)」からきていることはご存じでしょうか。句はちょうど、あじさいも帷子も同じような薄浅黄色をしているというような意味でしょうか。二つのものの色彩が鮮明に浮き上がる良い句だと思います。昔議会で担当部長が予算書の説明の折、浅黄色の間紙をはねてくださいと言っていたことも思い出しました。浅黄色を調べると、黄色・みどりより空色に寄った色だということがわかります。話があじさいから横にそれてしまいましたが。
芭蕉でもう一句「紫陽花や藪を小庭の別座舗(べつざしき)」があります。芭蕉が生涯最後の旅に出る時、門人の屋敷で開かれた句会で詠まれたものだそうです。大きなお庭ではなくそれほど手入れされていない、別座敷の庭に咲くあじさいの可憐で儚い美しさに、寂しさが込められた一句です。この句会は芭蕉晩年の門人子珊(しさん)の別座敷で開かれ、この句が発句、この句につづく脇は子珊がとって「よき雨あいに作る茶俵」であったそうです。梅雨の雨間、新茶の詰められた俵と季節を感じることができる句が続きました。
そして、正岡子規で一句「紫陽花や きのふの誠 けふの嘘」、あじさいは土壌の酸性の度合いによって花の色が変わります。酸性が強いと青に、アルカリ性だと赤色へ花の色が変わるそうです。このように色が変化することで「移り気なもの」「気まぐれなもの」「不確かなもの」の代表として詠われています。人の心の移ろいやすさを詠んだ代表句だと言ってもよいのでしょう。しかし土壌や開花の終盤になると色が変化することは、私にとっては楽しみの一つでもあります。
梅雨の時期、あじさいの美しさに一時現実を忘れるのはいいですが、この数年、毎年繰り返し発生する線状降水帯による大雨については、警戒する気持ちを決して忘れないでください。自分の命は自分で守ることが災害対応の基本です。まず自助、そして共助、公助は災害の規模が大きくなればなるほどその発動が遅くなることをご承知おきください。
令和6年5月
大型連休後半の最初の祝日5月3日は憲法記念日です。現在の日本国憲法は昭和21年(1946年)11月3日に公布され、翌昭和22年5月3日に施行されました。この記念日は「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」と定められています。
皆さんは日本国憲法の三原則をご存じだと思いますが、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」が大きな柱となっています。国民主権とは、民主主義の理念がその根底にあり、国の政治のあり方を最終的に決定するのは国民であるということを意味しています。我が国において現在では、18歳以上の成人の投票によって選ばれた代表が国民の代わりに政治を行います。
先日パリオリンピック聖火リレー中学生派遣事業で、駐ギリシャ日本特命全権大使伊藤康一閣下にお招きいただき、大使公邸で夕食をともにする機会を得ました。派遣団の私たち大人も、もちろん市内の中学生9人も食べ慣れた日本食に安らぎを感じ、元気を取り戻したひと時でした。冒頭のあいさつで伊藤大使は「ここアテネは世界で初めて民主主義による政治が行われた場所です」と語られました。中学2年生になったばかりの子どもたちにとっては少し分かりにくい話だったかもしれませんが、紀元前5世紀前後のアテナイ(アテネ)の民主主義は世界最初の民主主義として知られています。
アテナイの民主主義は、直接民主制でした。市民が法律や法案に直接投票をしたのです。アイスキュロスの悲劇「救いを求める女たち」には次のような一節があります。「民衆の手が頭上を埋め尽くす、右手がいっせいに挙げられた、満場一致だ、民主主義が民衆の決断を法律に変えたのだ」直接民主制の高揚した雰囲気を伝える文章です。
現代の間接民主制との違いが大きいのはもちろんですが、一番大きな違いは直接投票に参加できる「市民」とは成人男性であり、女性や在留外国人には参政権が認められていなかったことです。むろん当時労働力として存在した奴隷に対しては、人格の平等や基本的人権という概念も存在しなかったのです。
しかし、民主政治というものの発祥の地がアテナイ(アテネ)であったという事実に間違いはなく、パルテノン神殿から眺めるプニュクスの丘(世界初の民主的立法府「民会」が行われる丘)が、私たちに民主主義は機能しているかと問いかけているように見えたのは私だけでしょうか。
令和6年4月
今月16日にパリオリンピック聖火採火式が、本市の姉妹都市でありますギリシャ共和国オリンピア市で行われます。市内中学校9校の代表のうち、オリンピア市長によるくじに当たった1人がトーチを持ち、他の8人の伴走生徒とともにメインストリートを走ることになる予定です。
今月は古代オリンピックの由来について書きたいと思います。諸説ある中で一番興味深いと思う説を紹介いたします。
シピュロスの王ペロプスは、ピサの王オイノマーオスの娘ヒッポダメイアに求婚することにしたのですが、オイノマーオスは「婿の手にかかって殺される」という神託を受けていました。そのため彼は娘への求婚者に戦車競走をするように仕向けました。オイノマーオスの戦車を牽く馬は由緒ある名馬2頭で、ミュルティロスが御者を務めていたので、これまでの求婚者はオイノマーオスがゼウス神殿に祈りをささげている間先行をすることを許されていても、みな追いつかれ殺されていました。その数12人とも13人ともいわれています。
ペロプスは一計を案じ相手の御者であるミュルティロスに、王国の半分を与えるという魅力的な取引を持ち掛け承諾させ、戦車の心棒に蝋でできたくさびを差し込んでおくことに成功しました。競争が始まりペロプスは先行しますが、オイノマーオスが猛然と追いつき相手の背中をやりで突こうとしますが、まさにその時車輪が外れオイノマーオスは戦車から転落し、亡くなってしまいます。息絶える前にミュルティロスの裏切りに気づき、彼を呪ったといいます。
勝ったペロプスは、ミュルティロスとヒッポダメイアを乗せて戦車を西に走らせます。しかしミュルティロスとの約束を守りたくないペロプスは、岬の突端まで来ると彼を蹴飛ばし墜落させました。ミュルティロスは波に飲み込まれながら、ペロプスとその一族に呪いをかけました。何か呪いの掛け合いのようですね。
ペロプスは、妻の父であるオイノマーオスの王座を継ぐと勢力を拡大して、支配地の名前をペロポネソス(ペロプスの島)と改めました。ペロプスはさらにオリンピアも奪い取り、ギリシャ全土の名誉と尊敬の対象となったといわれます。しかし、ミュルティロスを殺した罪の償いとして、オリンピアの戦車競技場にミュルティロスの記念碑(ゼウス神殿という説もあります)を建て競技会を開きました。これがペロプスの死後も続き、古代オリンピックの始まりとなったという話です。
ギリシャ神話は、この話にも多くの枝葉があり多様なものですが、そんなギリシャ共和国オリンピア市で中学生がトーチを持ち、元気に走ってくれることを願っています。