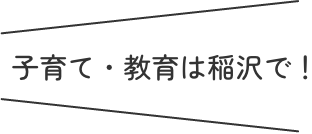健全化判断比率・資金不足比率とは?
- [更新日:]
- ID:738
健全化判断比率・資金不足比率の特徴
市の全体の収支や借り入れの状況に注目します
財政健全化法施行以前も、地方自治体の財政破たんの目安となる指標がありましたが、これは、「一般会計※1」と、「特別会計※2の一部」からなる「普通会計※3」を対象としたものでした。
一方、財政健全化法では、一般会計・特別会計・公営企業会計※4などを対象とし、市全体の財政状況に目を向けることになります。
稲沢市の各指標の対象会計等は、下図のとおりです。
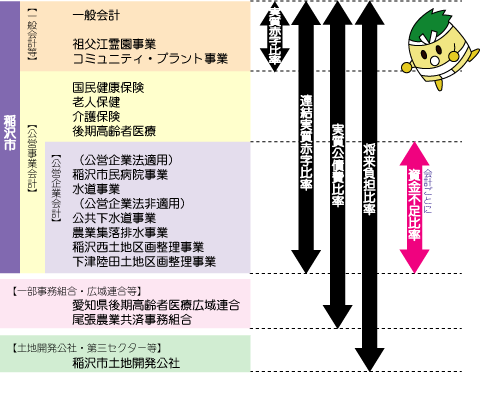
※「愛知県後期高齢者医療広域連合」「尾張農業共済事務組合」は、実質公債費比率・将来負担比率の対象に、また「稲沢市土地開発公社」は将来負担比率の対象になっていますが、稲沢市が負担すべき負債等がないため、比率の算出においては、算入されていません。
用語の説明
※1 一般会計:福祉、衛生、教育、土木など、基本的事業を経理する、市の予算の中心となる会計です
※2 特別会計:特定の事業を行う場合に、一般会計の歳入歳出と区分して設置した会計です。稲沢市には、国民健康保険特別会計など10つの特別会計があります。
※3 普通会計:一般会計、特別会計などで処理する事業の範囲が、地方自治体ごとに異なっているため、地方自治体間の比較ができるよう、統一的な基準により定められた、統計上の会計区分です。稲沢市では、一般会計、祖父江霊園事業特別会計、コミュニティ・プラント事業特別会計と、稲沢西土地区画整理事業・下津陸田土地区画整理事業の一部が、普通会計に区分されます。
※4 公営企業会計:民間企業と同じ考え方に基づいて会計処理するもので、本市では、「地方公営企業法」に従って経理を行っている、水道・市民病院の2事業が該当します。なお、公共下水道・農業集落排水・稲沢西土地区画整理・下津土地区画整理の4つの会計は、「地方公営企業法」に従って経理を行っていないため、「特別会計」としていますが、健全化判断比率・資金不足比率の算定においては、公営企業会計という扱いをします。
イエローカードとレッドカード
「健全化判断比率」(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率の4つの指標)には、「早期健全化基準」と「財政再生基準」が設けられています。
「早期健全化基準」については、4つの指標のうち1つでもその基準を超えると、「要注意」段階と見なされ、「早期健全化計画」を策定、その計画に従って自主的かつ計画的に財政再建に取り組まなくてはなりません。
「財政再生基準」は、4つの指標のうち「将来負担比率」を除く3つの指標がこの基準を超えると、従来の財政再建団体にあたる「財政再生団体」に指定され、国の厳しい指導・監督の下での財政の再建を行うこととなります。財政再生団体に指定されると、使用料・手数料や国民健康保険税が上がり、福祉・教育・道路などについて単独事業を行うことができなくなるなど、住民サービスのカットという事態に陥ります。
また、「資金不足比率」には、「経営健全化基準」が設けられており、その基準を超えた会計も、「要注意」段階とされます。
このように、2段階の基準を設けることで、財政状況の悪化の度合いを2段階に区分し、段階に応じた財政再建の取り組みを行うという仕組みとなっています。財政が完全に破たんしレッドカードが出される前に、イエローカードで注意を促すという制度で、人間に例えるならば、早期発見・早期治癒をして、重い病気になるのを防ごうということになります。
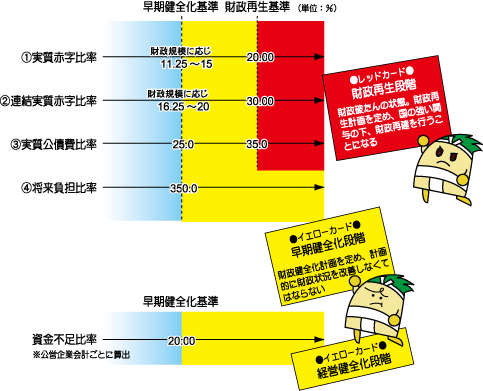
※連結実質赤字比率の財政再生基準は、3年間経過措置があり、平成21年度:40.00%、平成22年度:35.00%、平成23年度以降:30.00%となります
各指標の意味するもの
(1)健全化判断比率
実質赤字比率
一般会計等の実質赤字額の、標準財政規模に対する割合
標準財政規模とは、標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源(歳入のうち、使途が特定されずどのような経費にも使用することができる資金)の規模をいい、地方税や普通交付税など市が自由に使えるお金が、どの程度あるのかを示すものです。
「実質赤字比率」は、「市の基本的サービスを行う『一般会計』等の赤字額が、自由に使える財源に対し、どの程度の割合となっているのか」を示してます。なお「実質」という意味は、赤字額として、歳出額と歳入額の差額だけをいうのではなく、その年度に行うべき事業を翌年度に繰越した場合、その事業費分もその年度の支出に含めて計算するということになります。
赤字額が増え、この比率が高くなるほど、自力での赤字解消が難しく、深刻な状態になっているということになります。
連結実質赤字比率
全会計の実質赤字額(または資金不足額)の、標準財政規模に対する割合
実質赤字比率が、一般会計等だけの赤字額を対象としたのに対し、連結実質赤字比率では、市の全会計(一般会計・特別会計・公営企業会計)の実質の赤字額が、標準財政規模に対しどの程度の割合かを示しています。なお、「地方公営企業法」を適用する企業会計(水道事業・市民病院事業)では、赤字に相当する額として、流動負債から流動資産を差し引いた「資金不足額」を用います。
特別会計の歳入の一部は、一般会計からの繰出金で賄われています。また、公営企業会計は、料金などの収入を財源として、独立採算で事業を行うのが原則ですが、料金収入が十分でなく赤字が出る場合は、一般会計が赤字を補う場合もあります。ですから、赤字が膨らんでいる特別会計や公営企業会計があると、市の財政を脅かす恐れが生じます。そこで、全会計を対象とした赤字の度合いにも、注目するわけです。
実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金および準元利償還金の、標準財政規模に対する割合(過去3年度の平均)
地方自治体の借金を地方債といいますが、地方債の元金返済額と利子の支払い(元利償還金)を公債費と呼びます。一般会計の公債費のほか、公営企業会計等の他会計の公債費のために一般会計から繰り出した経費(元利償還金に準ずるもの=準元利償還金)などの実質的な公債費が、標準財政規模に対して、どの程度あるのかを示す指標です。
この比率が高いということは、通常の状態で見込まれる、使い道の特定されていない収入の多くを借金の返済に充てているため、他の事業に予算が回せなくなっていることを意味し、財政構造が硬直化に陥っていると言えます。
なお、計算にあたっては、都市計画税など公債費に充てられる特定財源や、地方交付税により措置のある財源等を除いて計算します。
将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
一般会計等が将来負担しなければならない負債には、一般会計等の地方債のほかに、公営企業会計等の負債の返済のために一般会計等が負担することが予定されているものや、契約等によって将来支払わなければならないもの(債務負担行為)があります。さらに、職員の退職引当金に相当するものも、将来の負担となります。
これら、将来負担額が、標準財政規模に対して、どの程度あるのかを示すのが「将来負担比率」で、将来、これらの負債が財政運営を圧迫する恐れがあるかどうかを見る指標です。早期健全化基準は350.0%となっており、これは、通常の状態で見込まれる、使い道の特定されていない収入額に対し、負債等が3.5倍以上あると、イエローカードということになります。(なお、将来負担比率には、レッドカード(財政再生基準)がありません)
なお、計算にあたっては、将来負担から、充当可能基金や、地方債残高に対する地方交付税の措置分を除いています。
(2)資金不足比率
資金不足比率
公営企業会計ごとの、資金の不足額の事業の規模に対する比率
実質赤字額もしくは資金不足額が、「事業の規模」に対し、どの程度の割合かを示す数字で、公営企業の経営状態を表すものです。「事業の規模」とは、「営業収益の額ー受託工事収益の額」で求められ、例えば、病院事業であれば診療収入などが、また水道事業や下水道事業あれば利用者からいただく利用料金などが、「事業の規模」に当たります。
資金不足比率が高いということは、料金収入等に対する資金の不足額が大きいことになり、料金収入だけで資金不足を解消するのが難しく、経営に問題があることになります。