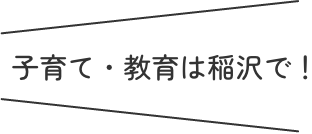市県民税の改正(令和5年度)
- [更新日:]
- ID:735
主な変更点は以下のとおりです。
住宅ローン控除の特例の延長等について
住宅ローン控除の適用について、適用期限が令和3年12月31日から令和7年12月31日まで4年延長となりました。また住宅ローン控除適用の所得要件が見直され、合計所得金額が3,000万円以下から2,000万円以下へと変更されました。
それに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の住民税から控除する措置について、以下のように変更が行われます。
住民税の住宅ローン控除限度額
- 入居した年月:平成21年1月~平成26年3月
控除限度額 A×5%(最高97,500円) - 入居した年月:平成26年4月~令和3年12月(注1)
控除限度額 A×7%(最高136,500円) - 入居した年月:令和4年1月~令和7年12月(注2)(注3)
控除限度額 A×5%(最高97,500円)
上記のAは、所得税の課税総所得金額、課税山林所得、課税退職所得の合計額です。
(注1)平成26年4月から令和3年の間に入居した方のうち、特定取得※1に該当する方に限られます。
(注2)令和4年中に入居した人のうち、特別特例取得※2に該当する場合は、(2)の場合の控除限度額と同じになります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
※1…新築、取得または増改築等に係る対価の額等に含まれる消費税額および地方消費税額の合計額が10%または8%の税率により課されるべきものである場合の住宅の取得等を指します。
※2…注文住宅は令和3年9月末まで、分譲住宅等は令和3年11月末までに契約を行い、令和4年末までに入居をした住宅で、新築、取得または増改築等に係る対価の額等に含まれる消費税額および地方消費税額の合計額が10%の税率により課されるべきものである場合の住宅の取得等を指します。
住宅ローン控除の控除期間
| 居住を開始した住宅 | 居住年 | 控除期間 |
|---|---|---|
| 認定住宅等 (認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・ 省エネ基準適合住宅)の新築住宅等 | 令和4年~令和7年 | 13年 |
| 上記以外の住宅新築住宅等 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
| 上記以外の住宅新築住宅等 | 令和6年~令和7年 | 10年 |
| 既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)時点で18歳、19歳のかたは市民税・県民税の非課税判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円を超える場合は課税されます。
(扶養人数等の要件により、非課税となる合計所得金額が変わる場合があります。)
セルフメディケーション税制の拡充および延長
セルフメディケーション税制について、その適用期限を令和4年1月1日から令和8年12月31日まで、5年延長することになります。
また、本特例の対象となる医薬品の範囲にも見直しが行われました。具体的には、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、OTC医薬品(医師の処方箋がなくとも薬局等で購入できる医薬品)に転用された医薬品)から療養の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認められるものを除外し、スイッチOTC医薬品と同種の効能または効果を有する要指導医薬品または一般用医薬品(スイッチOTC医薬品を除く。)で、療養の給付に要する費用の適正化の効果が著しく高いと認められるもの(3薬効程度)が対象に加わります。